|
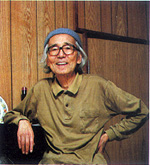 変化の時代は月日の流れも速い。アッというまに半年以上も経ち、旧聞となったが、昨年9月末、北京を訪れたときのことである。 変化の時代は月日の流れも速い。アッというまに半年以上も経ち、旧聞となったが、昨年9月末、北京を訪れたときのことである。
本誌の50周年祝賀会に参加し、旧友とも再会する主目的のほか、北京の変化、とくに目に見えない意識を体感しようと思ったのだ。
公的な催しのいきさつは本誌の昨年12月号で詳細が報道されているし、わたしごときが重ねて触れることもなかろう。
ただひとつだけ、盛大な祝賀会が、伝統のなかに新風を感じさせ、新風のなかに伝統を感じさせたということを記しておく。適度な型破りの式次第にも主催者の苦心が窺えた。
北京空港は7、8年ぶりだが、出迎えは輻輳していると思い予め謝絶していたので、娘と二人でタクシー乗り場に出て驚いた。待つ人ばかりで車は一台もいない。大渋滞でタクシーは敬遠してこないのだそうだ。と、車が止まり、青年がおりてきた。
「タクシー来ないよ。北京どこ行く?」
ハハア、白タクだなと思ったが、ホテルの名を言い、値段を聞いてみた。かねて聞いていた最近のタクシー値段の二倍あまりである。押し問答していると、娘が「仕方ないじゃない、乗りましょうよ」という。
因みに中国では白タクを「黒車」という。闇営業というわけだ。
不安がないでもなかったが、市内の風景が一変し、どこを走っているのか分からないわたしに、細かくガイドしてくれる兄イの北京語を聞いているうち、次第に安心した。
実は半分も聞き取れないのだが、市民の意識変化を見聞することも北京訪問の目標の一つだったので、怪しい中国語で問答する。
「先生は北京にきたことがあるのか」
わたしは、改革開放政策の始まった1978年に『人民中国』の「専家」(つまり外国人助っ人)として赴任以来、88年までの間に通算五年、北京に住んでいたことを話した。
ぐっと距離が縮まった。かれは、3人の仲間と共同で「仕事」しているのだといい、携帯電話の番号を書いたメモをくれた。
「電話してくれればすぐ来る」
そしてフロントまで重い荷物を運んだ。 記念行事がおわり、病臥中の康大川元編集長を見舞った後、父娘は一日を買物にあてた。
北京の買物事情もすっかり変わっているだろうから、かの白タク兄イに頼むことにした。電話すると、仲間に運転させ、かれは助手席に納まってやってきた。
半日の料金を聞くと、「終わってからでいい」という。あとでややこしくなるとも思わず、わたしは、そのまま頷いてしまった。
その日はカミサンからの指示と娘の希望とを優先し、買物に目的を絞って市内の四カ所を巡った。昼どき、丁度、瑠璃廠で注文した印鑑が出きるまでの間、一緒に食事をというと、清朝時代風の料理店に案内してくれた。味・雰囲気・値段、わたしも娘も満足度100%であった。多すぎて余ったのは、兄イたちにお持ち帰り願った。
娘の買いたい「太極拳の衣装」はどこで売っているのか? 兄イは携帯を掛けまわって調べ、王府井のスポーツ用品店にたどりついたが絹製がなく、これだけは目的が果せなかった。
夕方、ホテルに戻り、料金を聞いて面食らった。「先生が決めてくれた値段でいい」
冗談じゃない、決めようがない。押し問答をしていると、本気で「要らない」という。
わたしは困って一計を案じ、近くで客待ちをしているタクシーに「公定価格」を聞き、一件落着したのだった。
部屋に戻って考えた。改革開放が始まってほどなく、周知のように「向銭看」という言葉が流行した。「向前看」をもじった新語であり、市場経済のもと、全て金次第という風潮を皮肉ったものだ。
いまや市場経済は完全に定着し、合理的な「向銭看」は常識になった。だが、どっこい、計算づくの白タクお兄さんにも伝統的な人情は生きている。それも日本人の人情とは一味違い、『三国演義』や『水滸伝』の世界にもある独特な臭いである。
なぜ、白タク青年の意識などを大仰に書き立てるのか、奇異に思われるだろうが、改革開放政策の開始いらい四半世紀、歴史的な激変のなかで、中国人の意識がどう変わってきたか、わたしは深い関心と興味を持っている。
1980年前後のことだが、中国で、個人営業が許可されるようになったとき、上海では出願者がたちまち数千件に上ったのに、北京の出願者はごく少数と新聞が報じていた。いまでは思いもつかないことである。人々の意識と政治とのかかわりは、かくも顕著なのだ。
実はわたしは、禁欲生活に耐えてきた革命世代の老人たちが、現在の変化のなかで、どう感じているかをも聞きたいと思っていた。
で、学生時代の友人で今は亡き中国人の息子さんに会ったとき、何気なくその目的を話した。息子さんは四十代半ば、日本留学当時から旧知で、いまは大学の教師をしている。
思いもかけず、彼は即座にいった。
「それは止めたほうがいいでしょう。わたしの父もそうでしたが、激しく変化する時代のなかで、老知識人たちは悩みつつ、いま一定の精神的安定を得ているのです。外部から来て、突然その問題に触れるのは残酷です」
ガックンときた。確かにそうだ。ここまでの「独立思考」をする新世代人がいる。これまた中国知識人の意識変化を示す。しかもその底流に「敬老」という伝統的意識も複合されているというのは思いすごしだろうか。いや、起伏激しい歴史の荒波に育まれた中国的思考の奥行き深さを示すというべきか。
意識には時代に連れて変わってゆく部分と、変わらずに残る意識とがある。古い歴史を持ち、伝統的な思考遺伝子の強い中国人の意識変化は刮目すべきものがある。
一方、日本人自身の意識にも、この半世紀で激しく変化した部分、変わらない部分、複合された部分とが混在している。
互いにそれを擦り合わせ、理解しあってゆくことが、いま何よりも大事なことだと痛感したのが、旅の豊かな収穫の一つであった。
「意識」は、それを共有、もしくは理解し得る仲間うちにとどまっているかぎり、さほど問題ないが、それが一たび外部と接触すると、容易に「感情」へと発展しがちなのだ。そして「国民感情」「民族感情」ということになると、どの国であれ、これは厄介である。
まして、内にしろ外にしろ、何らかの要因によって誘発され、この感情に「狭隘な」という形容詞が付くようになると、恐ろしい。
日本と中国、これに朝鮮半島も加えて、東アジアは古い歴史を持ち、相互の関係史も、長く複雑で簡単には分析できない。
これに比し、アメリカは独立以来、僅か120年の人工国家で、南北戦争が終わって130年そこそこでしかない。日米関係、中米関係もさほど捩れておらず、分析しやすい。
実は小稿、白タク兄イの意識から始めて、いま瀬戸際に立つ日中間の意識差を、ザックバランに放談するつもりだったが、能力も紙幅も限界にきた。ゆるがせにできないこの問題、『人民中国』が、「本音の日中意識差シンポジウム」を開催するよう提案しておく。
最後に私的なことだが、老生は北京最後の日、不注意から入院騒ぎを起こし、本誌スタッフを始め、家族以上のお世話を受けました。貴重な紙面を借りて、深く深く感謝します。(2004年4月号)
|
