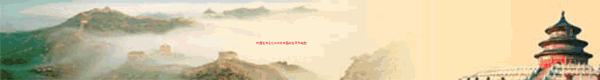
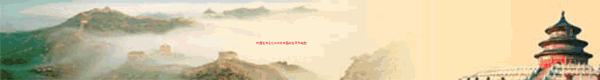 |
|
知られざる敦煌・楡林窟
|
|
今に残る玄奘と悟空の旅物語
|
|
段文傑
|
唐の僧、玄奘三蔵が仏教経典を求めてインドに行った物語は、『西遊記』の生き生きとした描写によって民間に広まり、中国はもとより、日本の人々にも親しまれている。この物語は早くも北宋の時代には巷間に流布し、『大唐三蔵法師取経記』『大唐三蔵取経詩話』などの話本(宋代に流行した講談本)にもなった。そこにはおなじみの「猿行者」(『西遊記』でいう孫悟空)も登場する。ご存知の通り、花果山の紫雲洞に住んでいた猿の王が、玄奘に付き従ってインドに行くわけだが、猿行者というのは彼が玄奘に弟子入りしてからの呼称である。 玄奘がインドに行く物語を題材とした絵を「唐僧取経図」といい、敦煌の壁画からはこれまでに六幅が発見されている。いずれも物語の由来とそれが流布していく過程を解明するための貴重な史料となっている。 六幅の唐僧取経図は、いずれも安西の楡林窟と東千仏洞で見つかった。 二幅目は、楡林窟第三窟西壁の普賢変に描かれている。平坦な地に茫々たる雲海が広がり、その下を流れる激流が玄奘らの行く手を阻んでいる。袈裟を身につけた玄奘は、普賢菩薩の後ろにそびえる仙山と楼閣を眺望し、合掌している。玄奘の脇では悟空が白馬の手綱を引き、師に従って祈りを捧げている。二人とも、長い行脚の末に疲れきった様子だ。白馬の背に乗せられた大きな蓮華の上で、経文を包んだ風呂敷きが光を放っている。この絵は玄奘がインドから657部の経文を得て持ち帰るところを表現しており、漢代に広まった「白馬、経文を駄せる」という物語(洛陽にある白馬寺に伝わる故事。インドからの僧を初めて迎え入れた時、経典を白馬に乗せたという)を基にしているのは明らかだ。 四幅目は、楡林窟第29窟北壁右側に見ることができる。水月観音図の下に枝葉を伸ばした大樹が描かれており、一人の民間人が玄奘と猿行者に話しかけている。猿行者と玄奘はいずれも側面から描かれており、猿行者の丸い目と大きな口が特徴的だ。彼は長髪の頭に金の輪をつけて包みを背負い、長衣のスリットから細口のズボンが見える。袈裟姿の玄奘は合掌し、微笑みを浮かべて話を交わしている。その後ろには鞍を背負った白馬がいる。 一方、北側の壁画では、玄奘が体を折り曲げて深々と頭を下げている姿が斜め前方の角度から描かれている。悟空の顔面部は欠損があるためその表情はよく分からないが、武将の着る上着を身につけ、片手で馬の手綱をひき、もう一方の手で金輪の付いた杖を持ち、首を傾げて遠くを眺めている。鞍を乗せた白馬は静かに立ったまま二人を待っている。この場面は、二人がインドへ経文を求めに行く途中の様子を描いたものだ。 * * *
一方の猿行者だが、やはり悟空と言った方が一般の方には馴染みやすいだろう。悟空は唐の玄宗時代に実在した長安・章敬寺の修行者で、もとの姓は車、俗名は奉朝といった。唐の天宝10年(751)、西域に出使した張光霄に従ってインドに行き、そこで重病を患ったため故国に帰れなくなってしまった。彼はそのままガンダーラ国に残り、インド各地、中央アジア、西域諸国を歴遊。27歳で出家し、60歳になって唐に帰国してからは章敬寺で経文の翻訳に従事した。『西遊記』に出てくる孫悟空は、このインドから突然帰って来た無名僧の姿に、後世の人々の想像が加わり、神格化されたものと考えられている。つまり、実際には玄奘と悟空は一緒にインドに旅したわけではないのだ。 一つは、古代中国の伝説――淮水の神、無支祁に由来するというもの。無支祁は猿に似た姿をしており、千変万化でいろいろなものに化けることができたとされる。この神様の物語は、唐の時代には民間にかなり広まっていた。 もうひとつの説は、古代インドの叙事詩『ラーマーヤナ』(王子ラーマが猿の軍隊の協力を得て、魔王ラーバナの手から妻のシーター妃を救い出す物語)に登場する神猿ハーヌマンに由来するというものだ。ここに描かれたハーヌマンの姿は、『西遊記』に出てくる孫悟空と多くの共通点がある。しかし、中央アジアから中国に至る仏教遺跡の壁画には、ハーヌマンの物語を描いたものが一枚もない。このため、孫悟空の姿形が『ラーマーヤナ』に由来するというこの説は、十分な根拠に欠けると言わざるをえない。 いずれにせよ、猿行者のイメージは伝説中のサエ水神を基に、仏教経典に描かれた物語の影響を受けて形作られたもの、つまり「混血の猿」と言っても良いかも知れない。唐僧取経図に出てくる猿行者であれ、『西遊記』に出てくる孫悟空であれ、どちらも機知に富み、勇敢で忠誠心に富み、暴力も恐れず、臨機応変に物事を処理する力と素朴な品性を持ち合わせている。それはいずれも中国の民族的、伝統的な美徳にほかならない。彼の絵が、千年以上経った今でもその芸術的生命力を失っていない秘密は、おそらくそこにあるのだろう。 * * * 先にも紹介した通り、壁画の唐僧取経図は、いずれも独立した絵としてではなく、観音変や普賢変の一画面として描かれている。これは玄奘と観音菩薩が、分かちがたい特別な関係を持っていたことの現われだ。その多くが観音変の中に描かれたのは、玄奘が自分を加護する仏として観音を崇拝していた証と考えられる。 水月観音が絵画の題材として描かれるようになったのは、唐代のことだ。中国画の歴史を記載した史書に「周ほう(日に方)は妙みに水月の体に創る」と記されている通り、仏教壁画の四大派を率いた宗教画家の一人周ほう(日に方)がその創始者である。 水月観音図では柳の枝と瓶を手にした観音が、峻厳な岩の上に座っている。その背後には何本かの竹が伸び、揺らめく池の水面に蓮の花が咲いている。そして彩雲に一輪の明月が掛かるという、静寂な幽境が描かれている。 白居易の詩に「静緑水の上、虚白は光中にあり、一たびその像を睹れば、万縁皆空なり」というのがあるが、この「空」とは仏教でいう「一切皆空」を意味すると同時に、美しい景色を見る中で得られる思想的な浄化作用を指している。 * * * 玄奘がインドに行った物語は、玄奘が生きていた時代にすでに民間に流布していた。北宋の景佑3年(1036)、散文家の欧陽修が友人と揚州の寿寧寺に遊んだとき、唐僧取経図の壁画を見たとされている。残念ながら、寿寧寺も壁画もすでに存在しないが、それだけに安西の楡林窟、そして東千仏洞で西夏時代の唐僧取経図が発見されたことは大きな意義があるといえるだろう。 唐僧取経図が安西の楡林窟で発見されたのは、ある意味で歴史的な必然ともいえる。先にも紹介した通り、玄奘は朝廷の命令に背いて密かに長安を出て、夜の闇に紛れて瓜州にやってきた。玄奘が経験した筆舌に尽くし難い困難の数々は、地元の人にも深い印象を与え、語り継がれていった。画工たちがそうした言い伝えを壁画に残したのは、むしろ当然のことといえるだろう。歴史上に実在した人物を、想像の中の神霊世界と結びつけることで成立した絵画の世界。ここに楡林窟壁画の一つの大きな特徴が形成されたのだった。 唐僧取経図は『大唐三蔵取経詩話』をもとに創作されたものである。造形芸術である壁画は、具体的なイメージを喚起し、分かりやすい芸術的イメージで見る人に訴えかける力を持たなければならない。唐僧取経図は、玄奘が辿った危険に満ちた道程と苦難に負けぬ超越的な精神の力を示すと共に、中国とインドの文化交流の厚みを今に伝えている。それは敦煌の各種の芸術が奏でる大オーケストラの一パートに過ぎないが、その歴史的価値と芸術的価値には極めて高いものがある。(2001年3月号より) |