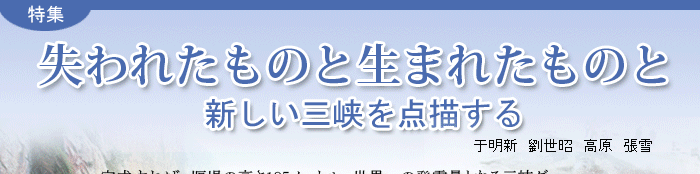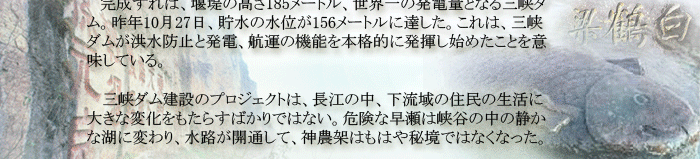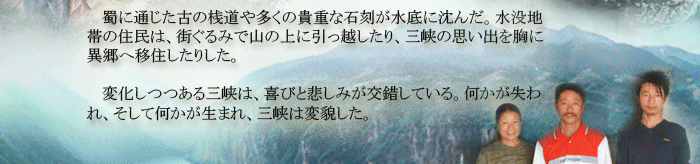|
三峡ダムの堰堤が締め切られ、水位が上昇するのに伴って、これまでは三峡下りの名所であった「小三峡」や「小小三峡」などの急流は、流れが広く緩やかになった。観光客は三峡のさらに奥まで行って、美しい風光を楽しむことができる。また、水位の上昇によって、新しい観光スポットが生まれ、三峡の「新景」は新たな魅力となっている。
「白鶴梁」――これは重慶市フ陵区城北の長江の中にあり、流れと平行して水中にのびる全長1600メートル、幅10〜15メートルの梁状の自然石である。伝説では、爾朱という道士が太守の恨みを買い、竹籠に入れられて水中に投げ込まれた。道士はここまで流れてきて、幸いにも漁師に助けられた。二人は親友の契りを結び、やがて道士は白鶴に乗って去っていった。そこから「白鶴梁」と名づけられたという。
「白鶴梁」はいつもは水の中にあり、毎年12月から翌年3月までの水の少ない時期だけ、水面にその姿を現す。当地の人々は、長江の水面が冬になって一定のラインにまで下がれば、次の年の気候は順調だと考えた。そこで人々は、「白鶴梁」に魚の絵を彫って標識にし、「石に歴史を刻む」やり方で長江の水位を記録した。
 |
 |
| (左)水没前の「白鶴梁」。1200年の長江の水位などの歴史を記録した「白鶴梁」は、「世界の水文史上の奇跡」と言われている (右)「白鶴梁」の水中博物館はすでに主体部分が基本的に完成した。完成すれば参観者は、水中に作られた廊下から、ガラス窓を通して、水中の石刻を見ることができる(写真提供・新華社) |
こうした習慣は、唐の時代から始まり、千年以上続いてきた。石の魚が水面に現れるたびに、人々は長江に集まり、文人墨客は「白鶴梁」の上に次々と揮毫した。これまでに「白鶴梁」上には18尾の石魚が彫られ、1200年間に72回の渇水の年があったことが記載されている。また、計3万余字の文字が彫られ、その中には、黄庭堅、朱熹、王士禎ら著名人の墨跡の石刻もある。
「白鶴梁」は世界で最初にできた「水文調査所」であり、中国の書道や絵画芸術の「水中の宝庫」であるということができる。
しかし、三峡ダムの貯水が135メートルの高さに達した後は、「白鶴梁」は40メートルの水の中に、永遠にその姿を消してしまった。そこで、「白鶴梁」を保護し、人々が引き続き貴重な石に刻まれた作品を鑑賞できるように、水面下に水中博物館を建設することが決まった。
1993年から2000年までに、5つの計画案が検討され、最終的に上海交通大学の葛修潤教授の「無圧容器」案に落ち着いた。この計画案によると、まずアーチ型の長さ70メートル、幅約23メートルの大きな保護の覆いを作り、その外側を鉄筋コンクリートで固める。そして、洗面器を裏返しにするように保護の覆いを水中に沈め、「白鶴梁」の石刻の中でもっとも素晴らしいものをその覆いの内側に囲い込む。さらに覆いの中に浄化した河川の水を注入し、覆いの内外の圧力を平衡させる。こうして石刻が、汚れた河の水に削られるのを防ぐ。観光客はエスカレーターで水面下に降り、覆いの中の透明な回廊から、ちょうど水族館のように石刻を鑑賞することができる。
水中博物館は2007年上半期に完成する予定だ。
重慶市豊都の鬼城は、三峡遊覧では必ず訪れる観光スポットの一つである。その独特な「鬼の文化」によって、鬼城は有名な、歴史と文化の小さな鎮となった。
しかし今、水位が変わったため、豊都付近の景観も変わった。豊都の県城はすでに移転した。鬼城は水没を免れたが、水がすぐ近くまで迫ってきた。その一方で、多くの新たな観光スポットが生まれた。豊都の新県城から十数キロの地点に新たに開発された鍾乳洞の「雪玉洞」もその一つだ。
 |
 |
三峡プロジェクトの全景(写真・鄭家裕)
|
豊都県の「雪玉洞」 |
1997年の春節(旧正月)、退職した幹部の王成雲さんは、鬼城の対岸にある竜河峡の辺で、偶然に鍾乳洞の入り口を発見した。彼はすぐに仲間を集めて、鍾乳洞の探索を始めた。半月の調査の結果、鍾乳洞の中には多くの純白な鍾乳石があり、洞内は広く、壮観であることがわかった。
「雪玉洞」は面積は大きくないが、全長1166メートルの参観ルートがすでに開発されている。洞内の景観は「白きこと雪の如く、質の純なること玉の如し」と言われ、「雪玉洞」と名づけられた。
専門家の分析によると、「雪玉洞」は世界の鍾乳洞の中でめったにない「妙齢の少女」だという。一般に鍾乳洞の鍾乳石の景観は、数万年前あるいは数十万年前から形成される。だから鍾乳石の質は老化し、色彩や光沢は暗いのが常だ。しかし「雪玉洞」の中の景観はだいたい3300年前あるいは1万年前から形成され、あたかも娘盛りのように急速に成長する時期にある。鍾乳洞内の堆積物は純白であるばかりでなく、生長速度が百年で33ミリに達する。これは普通の鍾乳洞の33倍である。
また、「雪玉洞」は珍しい「白い大理石の彫塑博物館」でもある。洞内の堆積物が造った景観は、さまざまな種類がすべてそろっていて、規模が大きく、形が美しい。その中に、現存する最長の、2.5メートルの「鵞管石」(円管状の鍾乳石)や、きらきらして透き通るような石筍や石柱、紙のように薄く透き通った石のベルト、風を受けてはためく石の旗、大きな迫力の石のカーテン、天から流れ落ちる石の瀑布、巨大な石の盾や塔状の洞窟珊瑚がある。
これまでは一部の鍾乳洞では、熱を発する光源を採用していたが、これは鍾乳石に損害を与え、多くの鍾乳石が光線によって黒くなり、もろくなるばかりでなく、生態環境にも変化が起きた。これを教訓に「雪玉洞」では、とくに費用のかかる熱を発しない光源を使用し、貴重な景観には保護の覆いをかぶせた。これによって、「雪玉洞」の鍾乳石の質の良さを強調している。
湖北省にある神農架は、古代神の神農氏が百草を嘗めたところと伝えられ、中国のみならず世界の中緯度地区で唯一、亜熱帯の森林生態系が完全に保存されているところである。ここは動植物の資源が豊富で、夏は涼しく冬は湿潤である。「山すそが盛夏になれば山頂は春、山麓が美しい秋になれば山頂は凍る。赤橙黄緑、いくら見ても飽きず、春夏秋冬は分かちがたし」――これは神農架の気候をうまく描写している。
以前は、三峡から神農架に行くのは水路が狭く、困難と危険がいっぱいで、実に不便だった。現在は水路が広くなり、客船に乗って神農架まで直行することができる。三峡と神農架という二つの大きなツアー・スポットが一つにつながった。
 |
 |
| (左) ここで、「野人」の住んだ痕跡が見つかったといわれる (右) 神農渓は神農架の山間部にその源を発する
|
神農架の名を高めているのは、珍しい原始林のほかに、伝説的な「野人」の存在の可能性である。「野人」は全身、深い毛に覆われ、直立して歩く霊長類で、清代に著された『房県志』には「房山(今日の神農架)には毛人多く、その長は丈(約3メートル)に余る」と記されている。
中国にはこれまでに「野人」を見たと称する人が360人以上いる。目撃談の一つを紹介すると――
1993年9月3日の朝のことである。ある工場の運転手、黄先亮さんは、マイクロバスに十数人の専門家を乗せて、国道209号線を走っていた。突然、前方20メートルぐらいのところを、3つの人影が並んで歩いてくるのを発見した。その中の一人はやや太っていて、車の方をじっと見つめていた。黄さんは「野人だ」と直感し、急いで車を停めた。専門家たちも車を降りた。するとその3人は、道路の脇の斜面へ走り去り、両手で力強く、木の枝や藤蔓を押しのけ、巨大な身体を密林の奥に消してしまった……
しかし、「野人」の存在は、科学的に確認されたわけではない。中国科学院はこれまでに2回、神農架の「野人」に対する大規模な調査を行ったが、「野人」を捕捉したり、目撃したりすることはできなかった。だが「神農架には確かに、一種の大型で直立歩行することのできる高等な霊長類の動物が存在している」とし、「大規模の、長期的な、更なる調査を引き続き行う必要がある」との結論を下した。
神農架から南へ行くと、神農渓に達する。神農渓を行くには必ず、舟引き人夫の引く「豌豆角(エンドウ豆のサヤ)」と呼ばれる小さな木造の舟に乗らなければならない。この地方独特の舟は、形がエンドウ豆のサヤに似ている。普通は長さ13メートル、幅1.8メートル。
 |
 |
| (左) 1992年に撮影された巴東神農渓の船引き人夫たち
(右) かつては舟が通わなかった神農渓の上流は、今日、観光客たちが舟引き人夫の引く舟旅を体験できる。山に住んでいた住民も、「豌豆角」と呼ばれる木造の舟に観光客を乗せ、収入を得ることができるようになった |
以前の神農渓は水深が浅く、流れが急だったので、川を溯るとき、浅瀬に遭うと、舟引き人夫が舟を降り、河原や崖の上から舟を引っ張って浅瀬を越した。川を下るときに急流に遭うと、逆に舟を引っ張って、舟の速度を緩める。これを俗に「牛を後ろに引く」という。
天気が暑いときは、舟引き人夫たちは、着物を全部脱いで真っ裸になり、掛け声を掛けながら舟を引く。裸になるのは、濡れた着物が身体に貼り付いて皮膚をこすり、抵抗が大きくなるからだという。
彼らが渾身の力で舟を引く姿は、神農渓独特の風景だったが、近ごろは観光客が増加し、全裸はまずいということになった。しかし、全裸は消えたが、舟引き人夫の澄んだ掛け声は、今も谷間にこだましている。(2007年2月号より)
|