文人画と日本
劉檸=文
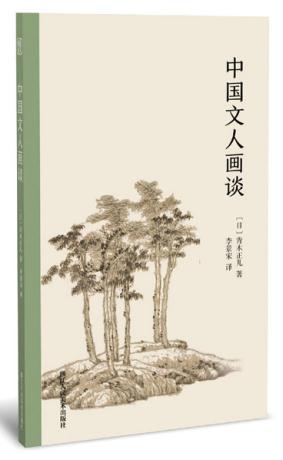
『中国文人画談』
『中華文人画談』
青木正児 著 李景宋 訳
浙江人民美術出版社
2019年6月第1版
中国画には一貫していわゆる「雅俗の別」があり、文人画は「雅」で、職人画が「俗」である。清代の盛大士は画論『谿山臥遊録』の中で、「画には士人(知識人)の画があり、作家(職人)の画がある。士人の画は玄妙で技巧を必ずしも必要としないが、作家の画は技巧があれば玄妙は必要とされない。ゆえに技巧があっても玄妙がないものは、玄妙があり技巧がないものには及ばない」と言っている。私見では、この言葉が中国画の雅俗の問題について言い尽くしたものであるように思う。
日本では、文人画は南画とも呼ばれている。漢学の大家である内藤湖南は、『中国絵画史』の中で、「中国の芸術史、殊に絵画史を極めて簡単に説明すれば、つまり長い間の中国の芸術の変遷は、結局南画というものを形づくるために進み来たりつつあったと言ってよいと思う」と記している。ここからも日本人の文人画の崇拝を見て取ることができ、文人画を絵画史と同等に見なすほどであったことが分かる。またもう一人、中国芸術に通暁していた青木正児は、1926年に東北帝国大学文学部中国文学講座の初代教授に就任した際、文人画に関する課程を開設している。今回紹介する『中華文人画談』は、ここでの講義に、加筆・修正を加えたものだ。青木が120㌻もの紙幅を費やし、文人画の歴史を整理しようとしたことは、平凡な学術的野心ではないと言える。
最も早く文人画という概念を唱えたのは、北宋の文学者である蘇軾(1037~1101年)である。当時、職業画家が千編一律の風格の絵を描いていたのに対し、士大夫たちの独特で斬新な画風が注目を集め始めていた。それ以降、文人画という意識は強まる一方で、最終的に明代末期の董其昌(1555~1636年)らに至って最高峰に達した。董其昌は『画禅室随筆』の中で、画壇を南北二宗に分け、宮廷画院の形を踏襲するものが北宗で、南宗は「文人の画」であるとしていて、これが文人画が南画とも呼ばれるゆえんである。
文人画は日本の芸術に深い影響を与えた。南宋の画僧である牧谿和尚(法常法師)の絵は色彩を用いず、線描を主として、巧妙に墨の濃淡によりぼかし効果を生み、極めて禅意に富むものとなっている。中国では全くの無名だが、その作品は室町時代の日本人に高く評価され、とても人気があり、日本の禅画に直接的な影響を与え、いまだ日本の博物館や京都の大徳寺などの寺院にその作品を見ることができる。
16世紀末、豊臣秀吉が手柄を立てた武将に褒賞を与えた際、中国からもたらされた水墨画を土地の代わりに与えたとも言われており、その貴重さがよく分かる。その時、日本の伝統的な大和絵はすでに活力を失っていたが、中国の水墨画の技法を吸収することによって復活した。江戸時代中期から、祇園南海、柳沢淇園、池大雅、与謝蕪村らの日本の画家は懸命に中国の文人画から学ぼうとし、南画派を創始した。幕末から明治初期にかけて、再び文人画ブームが起き、その後の新南画運動を引き起こした。文人画はとうとう茶や禅宗などの歴史上中国からもたらされた文化と同じように、「あなたの中に私があり、私の中にあなたがある」というような、所属があいまいなものとなり、後には題材があまり日本的ではない水墨山水画は、その落款を確認するまで、中国の文人画なのか日本の南宗画なのかはっきりしないなどという事態が引き起こされるようになるのだ。